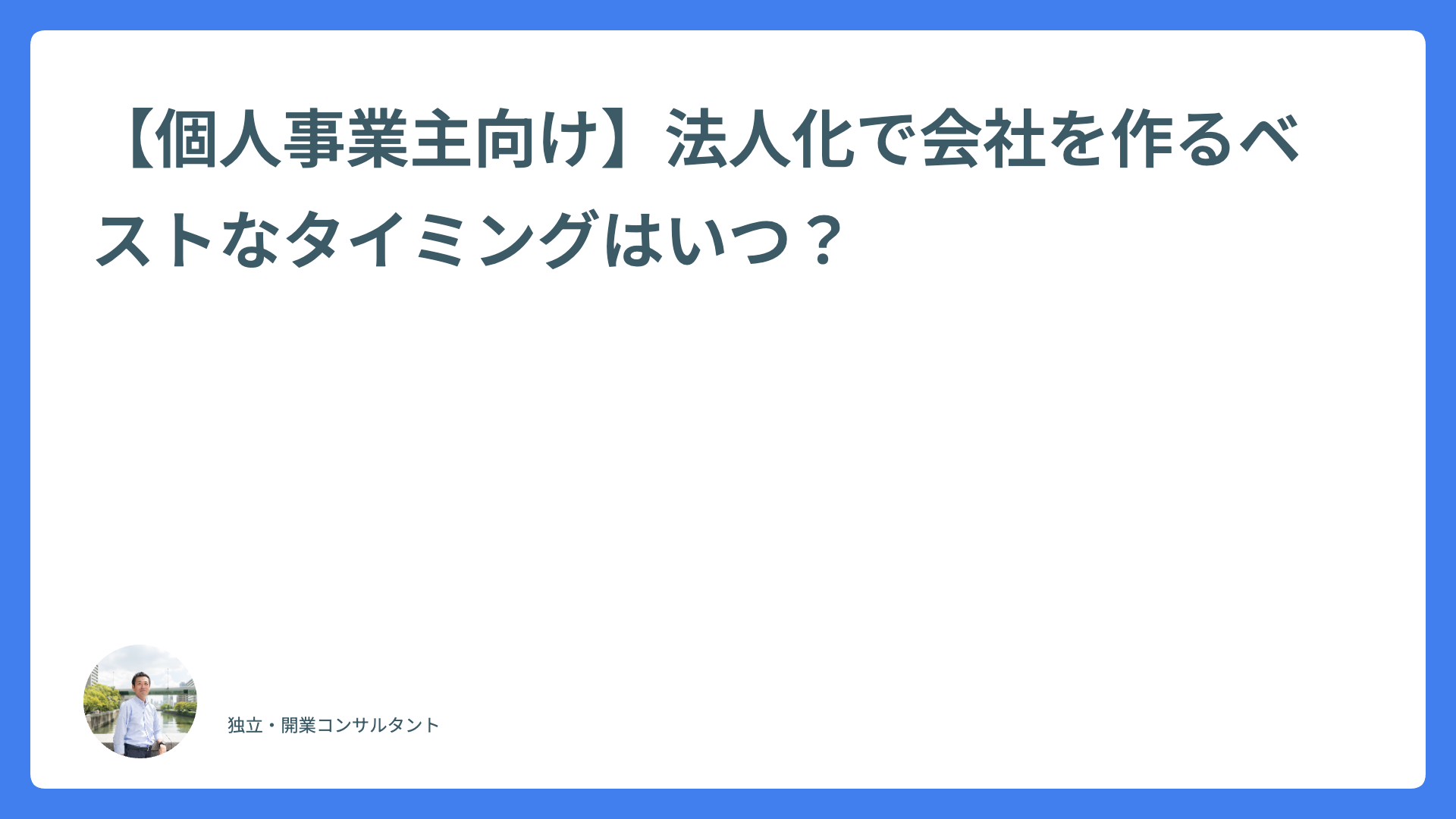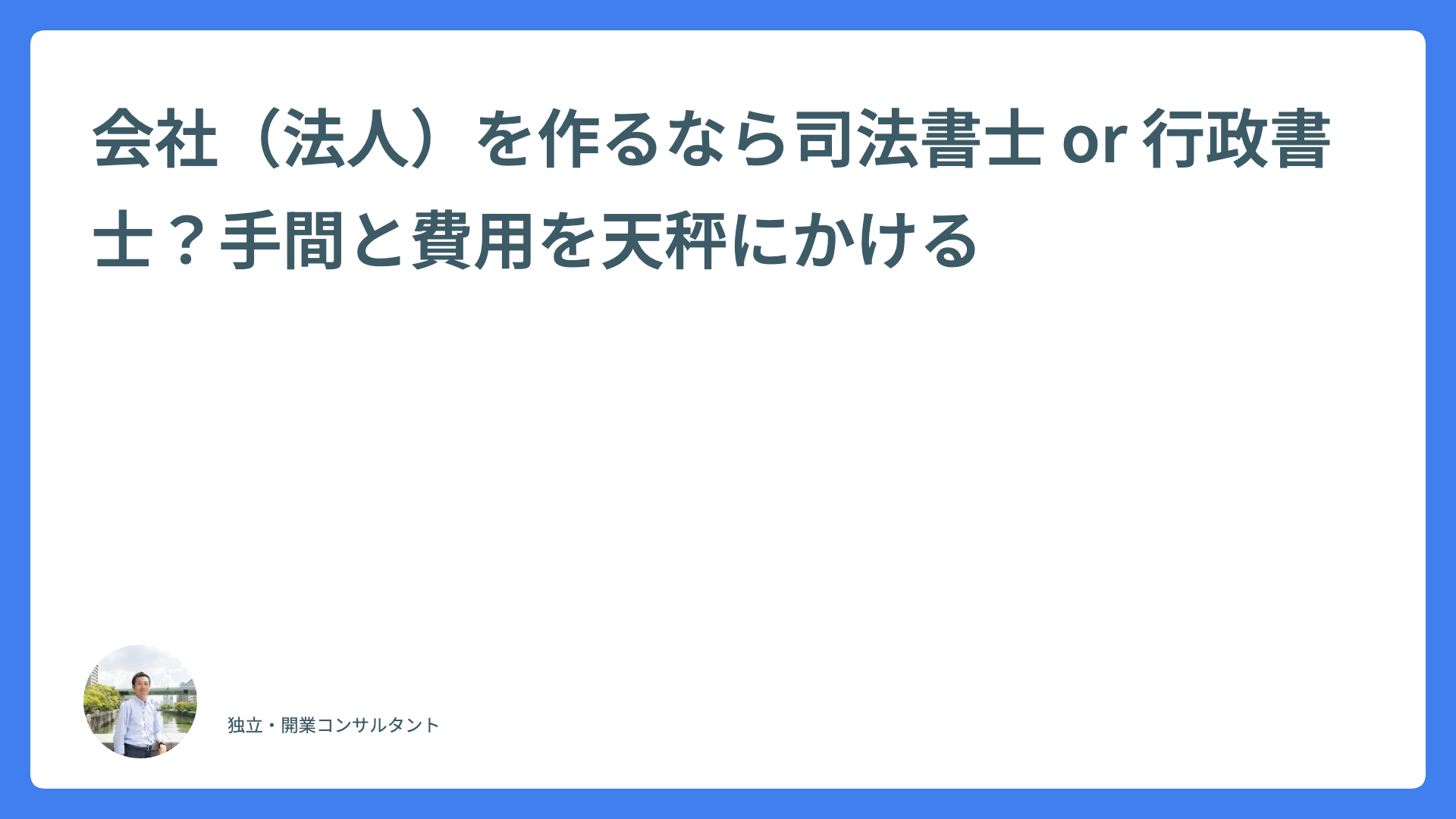法人化による給与設定。自分と家族の給料はどうやって決める?
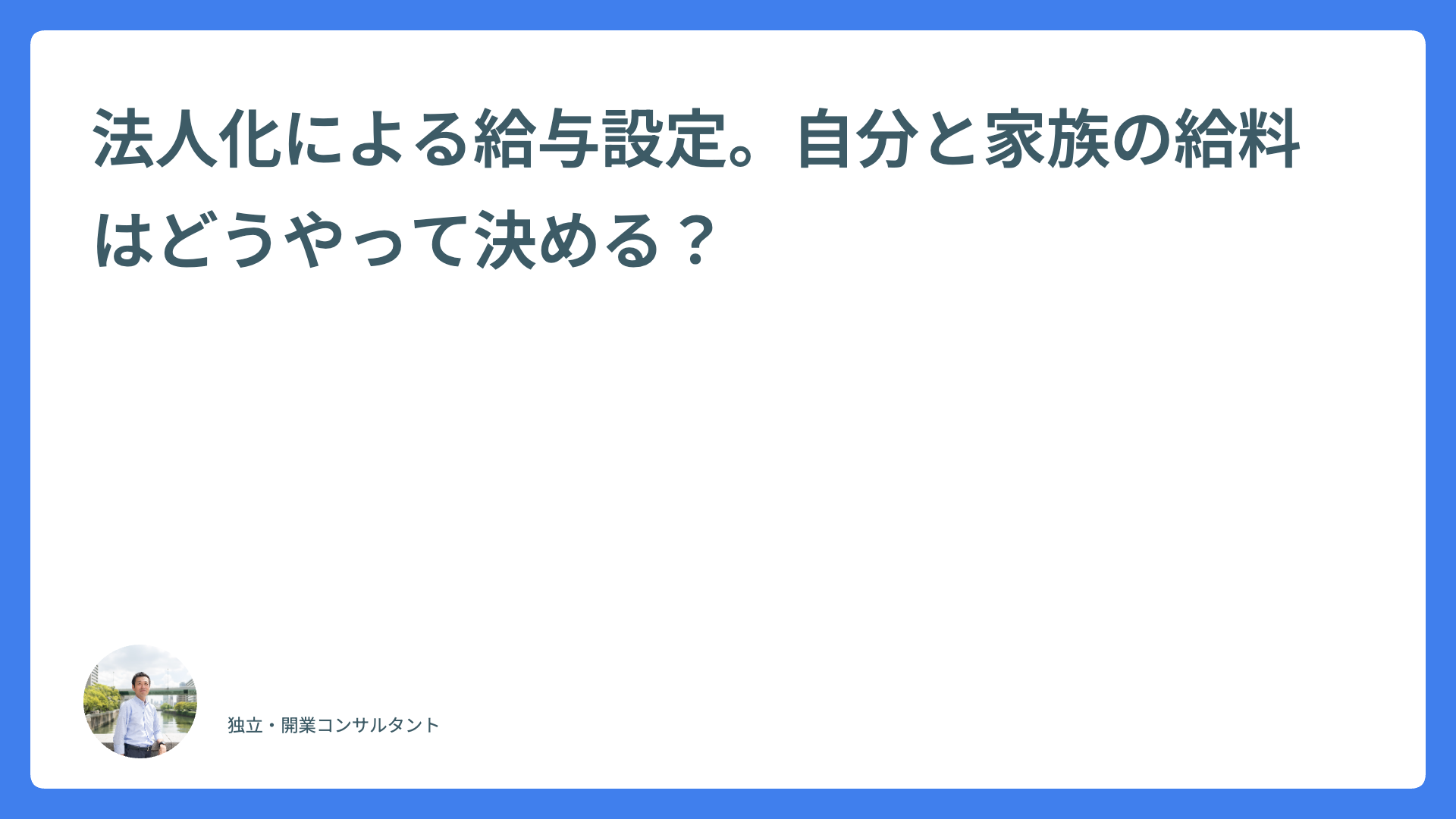
<プロフィール・ご依頼>
Contents
法人化による給与設定
個人で事業営んでいたかたが会社をつくると、決めることがいくつかあります。
その一つが、自分の給与をいくらにするか?
個人だと、自分に給与を支払うことはできませんでした。
そのため、利益が出たら、所得税がダイレクトにかかってきます。
これを回避するために、節税対策の一貫として法人化されるかたは多いです。
では、いざ会社ができたら自分の給与をいくらにすべきかについて考えてみます。
自分と家族の給料はどうやって決める?
自分への給与
法人化すると、自分への給与は「役員報酬」となります。
役員報酬は、法人税法でいくつかルールが定められています。
このルールを守らなければ経費として認められません。
- 金額の固定 一度決めた役員報酬は、事業年度中、毎月同額を支給しなければなりません。途中で変更すると、差額分は経費として認められません。
- 決定時期 事業年度開始日から3ヶ月以内に、役員報酬の金額を決定する必要があります。
個人の頃だと、必要な生活費を事業用口座から好きなタイミングで引き出すことができましたが、法人にしたら設定した給与以外の金額を安易に引き出すことはできません。
仮に、給与以外の金額を引き出すと、会社から個人への貸付金と見なされ、決算書に計上されます。
そのため、役員報酬を設定する際は、会社の資金繰りが成り立つ範囲内で、なおかつ、自身の生活費をまかなえる金額をシミュレーションして決めます。
シミュレーションは、キャッシュフロー表を作成し、今後1年間の売上や経費・生活費を予測して検討することをおすすめします。
家族への給与
個人事業主だと、家族への給与を経費にするには「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要でした。
法人だと会社と個人が別の存在と見なされるため、このような届出は不要です。
自由に給与を設定できますが、会社の資金繰りを考慮することが大事です。
家族が役員でなければ、給料の額は事業年度中、いつでも変更できます。
この点についは、個人の専従者給与だと、届出た金額の範囲内でしか支給できないので、法人のほうが使い勝手いいですね。
また、専従者への未払給料は必要経費になりませんが、会社だと未払でも経費になります。
人件費割合と労働分配率
自分の給料だけでなく、家族や従業員への給与が適正な水準かどうかを判断する際には、「人件費割合」や「労働分配率」が参考になります。
- 人件費割合: 売上高に占める人件費の割合
- 労働分配率: 売上から変動費(仕入れなど)を差し引いた粗利益に占める人件費の割合
とちらも人件費をチェックする指標ですが、労働分配率のほうがより正確に事業分析できます。
業種ごとのおおよその数値を把握しておけば、自社の給与設定が適正な範囲に収まっているかどうかの目安にすることができます。
(参考)中小企業庁による業種ごとの人件費割合の目安
- 製造業 20%前後
- 小売業 10%〜20%
- 卸売業 7%前後
- 建設業 15%〜30%
- 情報通信業 30%前後
- 飲食サービス業 30%〜40%
あくまでの目安ですので、自社の数値推移を把握し、他の経費とのバランスや資金繰りを考慮しながら加減すると良いですね。
まとめ
法人化における給与設定は、税法上のルールを守った上で、資金繰りと自身の生活費のバランスを考慮すること。
この3つの要素を総合的に検討しながら給与額を決定しましょう。
法人成りコンサルティングの「役員報酬の設定」では、役員報酬を4パターン設定し、法人税・所得税・住民税・社会保険のトータル金額で比較します。
ご興味ありましたらお声がけください。
法人成りコンサルティング
<メルマガ「独立・開業メールマガジン」>
毎週月・木曜の正午に配信。
法人・個人問いません。独立されているかた向け。
駅のホームで電車を待ちながら読めるくらいの内容です。
メルマガに対する質問や疑問にも応えます。
こちらから
<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<単発・スポット>