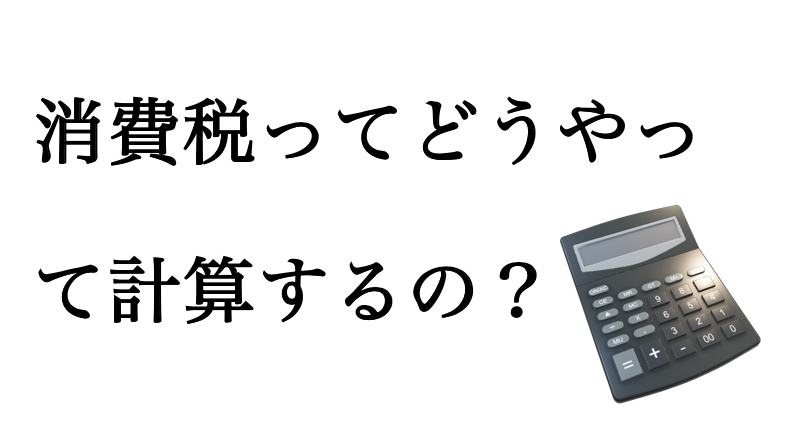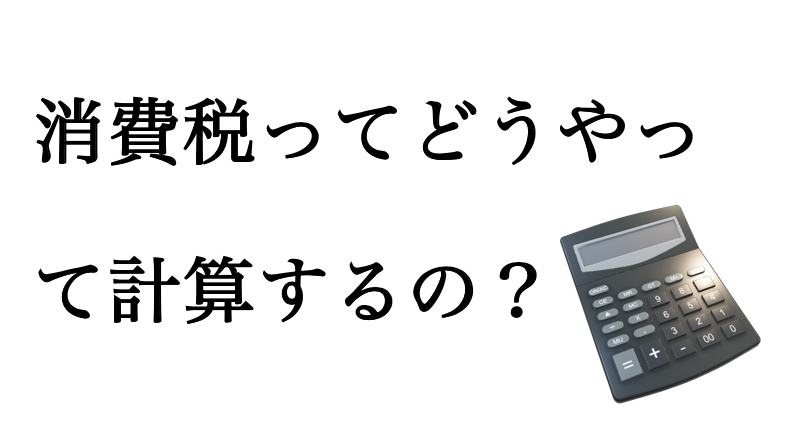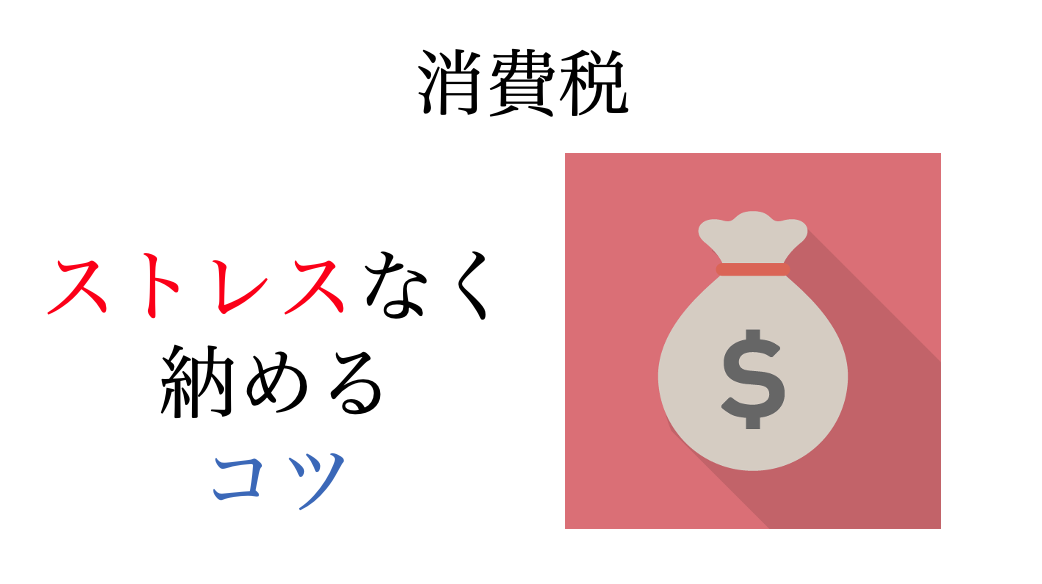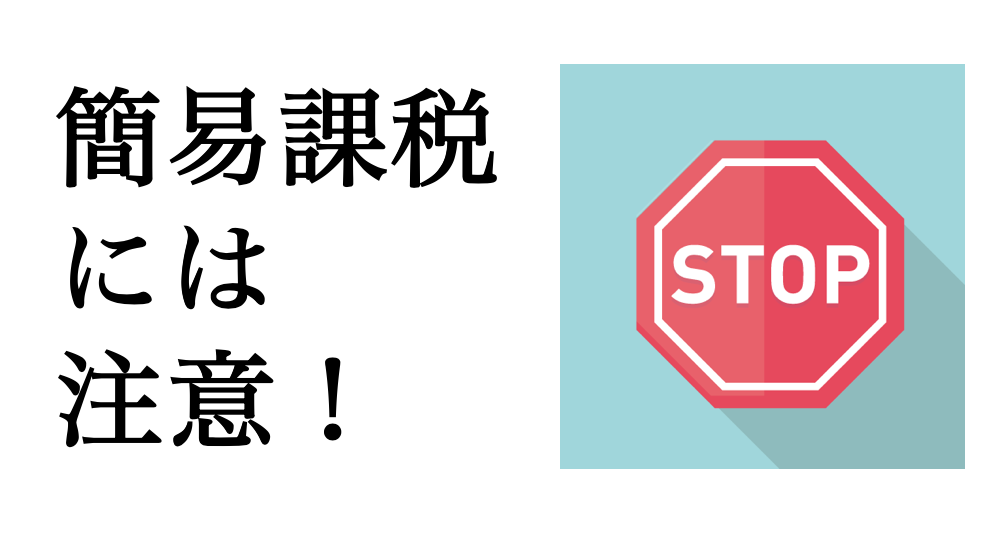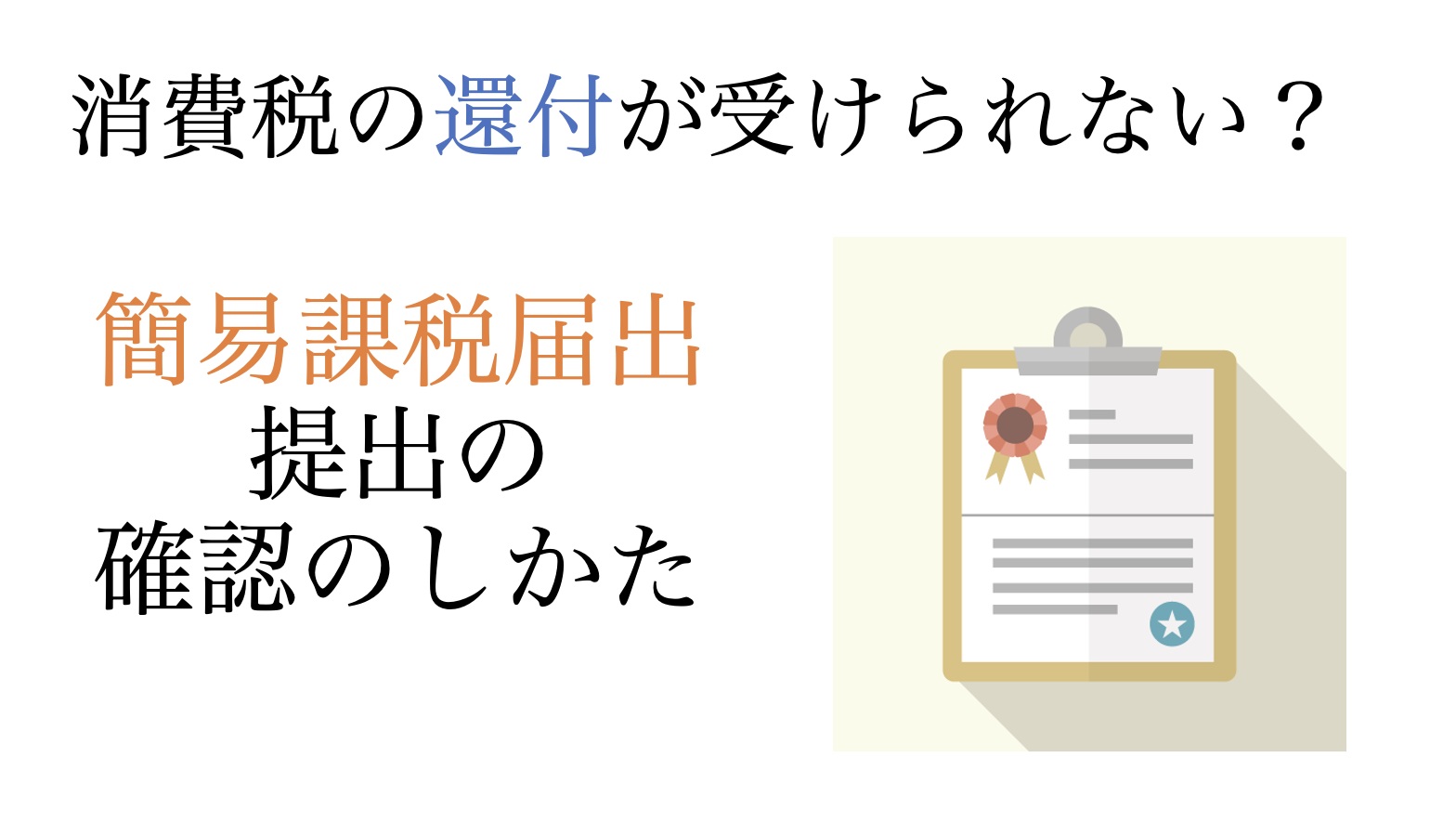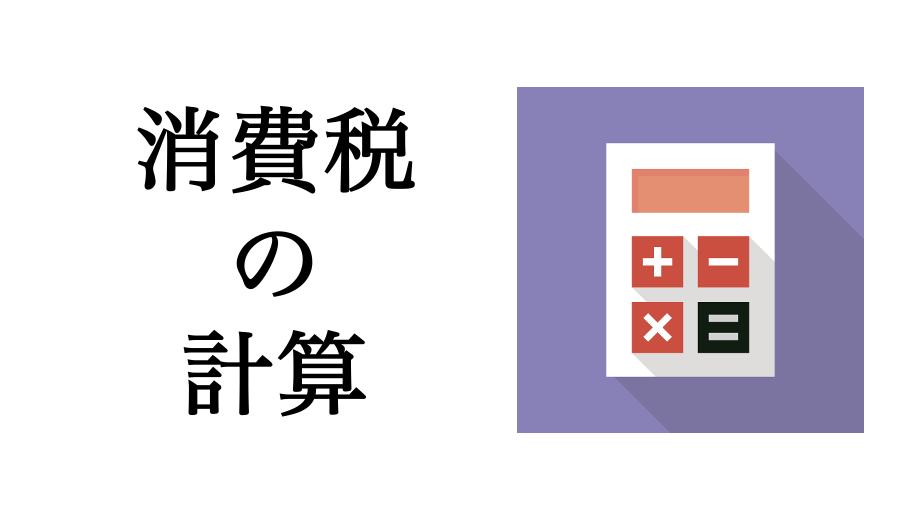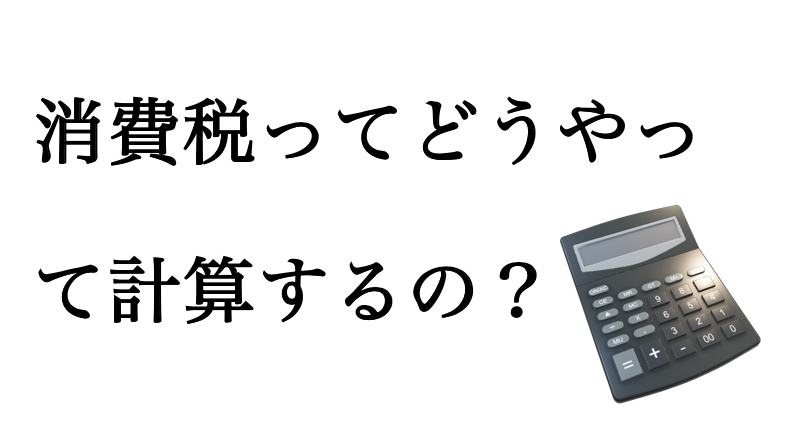
消費税の計算方法は選択できる
いち消費者として消費税に触れる機会は、モノを買ったりサービスを受けたりするときだけです。
コンビニや街なかの商店で支払いをすると本体価格には消費税が含まれています。
この消費税を実際に国に納めるのは、そのコンビニであったり商店であったりします。
私達が支払った消費税を、それらのお店がそのまま国に納めているのかというと少々違います。
では、どういった計算をしているのかというと、
そのお店がもらった消費税から払った消費税を差し引いた金額を国に納めます。
もらった消費税は私達が支払った代金に含まれる消費税であり、
払った消費税は仕入れた商品や経費に含まれる消費税です。
そのまま差し引きすれば済む話です。
このオーソドックスな計算方法を「一般課税」や「本則課税」などと言ったりします。
ただし、消費税の計算方法には「簡易課税」という特例があります。
簡易課税では、払った消費税を業種を使って簡便的に計算することができます。
「簡易課税」の基本ついて
一般課税と簡易課税は、納税者が有利な方を選択して適用することができます。
ただし、原則は一般課税であり。簡易課税の適用を受けるのであれば事前に届け出する必要があります。
利用できるのは?
簡易課税を利用できるのは売上が5,000万円以下の中小のみです。
個人か法人かは問いません。
小規模事業者に対する優遇税制です。
提出期限
有利な税制の適用を受けるには事前の届け出が必要です。
簡易課税の適用を受けるには、
- 個人であれば適用を受ける年の前年12月31日までに
- 法人であれば適用を受ける事業年度開始の日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
業種区分
一般課税と簡易課税は、仕入れた商品や経費に含まれる消費税の計算が大きく異なります。
これらの払った消費税のことを、消費税法では「仕入税額控除」と言います。
簡易課税では、この仕入税額控除の金額をその事業者の営む業種によって決めることができるのです。
業種は大きく分けて6つあります。
第一種・・・卸売業
第二種・・・小売業
第三種・・・製造業
第四種・・・その他の事業
第五種・・・サービス業など
第六種・・・不動産業
仕入税額控除の金額は、その年の売上(消費税の対象となる)に対して、
それぞれの割合を乗じて計算します。
割合は、順に、
- 第一種・・・90%
- 第二種・・・80%
- 第三種・・・70%
- 第四種・・・60%
- 第五種・・・50%
- 第六種・・・40%
第一種(製造)と第二種(小売)は共に仕入れた商品を加工せずに販売する事業です。
販売先が事業者か消費者で異なります。
仕入れた材料を自社で加工している場合は、製造業の第三種に該当します。
サービス業は第五種、不動産業は第六種に該当し、ここまでに含まれない事業と飲食業が第四種(その他事業)となります。
先を見添える
一度、簡易課税を適用すると、2年間はその計算方法を継続しなければいけません。
そのため、大きな資産(ただし、事業に関係があるもの)を購入する予定があれば、簡易課税ではなく一般課税のままの方が有利となります。
簡易課税にしてしまうと、その資産の購入で払った消費税を仕入税額控除に含めることができないからです。
簡易を選択したことによるリスクがあることも念頭に置いておきましょう。
<メルマガ「独立・開業メールマガジン」>
毎週月・木曜の正午に配信。
法人・個人問いません。独立されているかた向け。
駅のホームで電車を待ちながら読めるくらいの内容です。
メルマガに対する質問や疑問にも応えます。
こちらから
<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<単発・スポット>
ABOUT ME